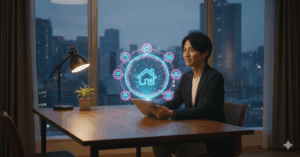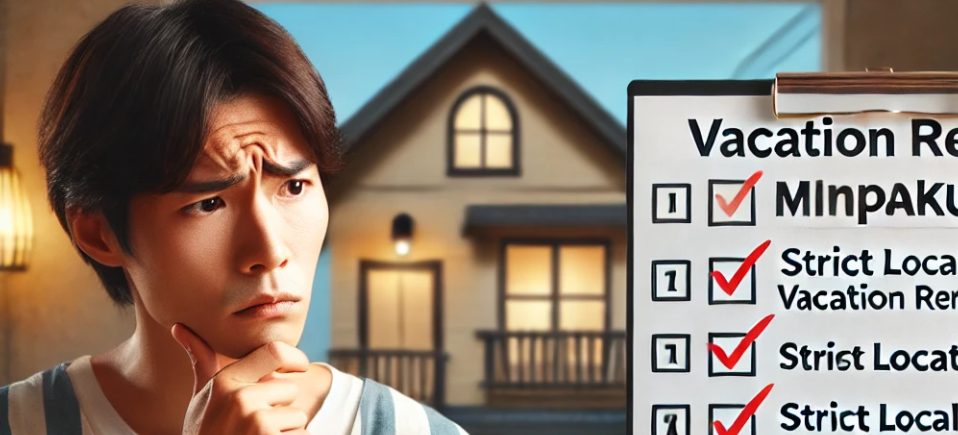
民泊運営代行ならお任せください
完全無料 オンライン相談民泊ビジネスが多くの人々に認知されるようになった一方で、参入のハードルが低いと感じて軽い気持ちで始めた結果、思うような収益が得られず途中で挫折してしまうオーナーも少なくありません。物件を用意し、ホームステージングや撮影を行い、予約サイトに掲載すればすぐにゲストが来てくれると思いがちですが、現実には物件そのものが民泊に適していない場合があります。
いくらクリーニングや写真撮影を頑張っても、思いもよらない落とし穴によって稼働率が伸び悩むことになるのです。そこで本記事では「民泊はやめておいた方がいい物件の特徴」と題し、一見すると問題なさそうに見えても、実際に運営してみると苦労が絶えない、あるいは全く収益が上がらないリスクをはらんだ物件のパターンについて深掘りしてみたいと思います。
もし物件選びの真っ最中であれば、ぜひここで取り上げる点を参考にしながら検討を進めていただければ幸いです。
エレベーターのないマンションやアパート
民泊において、チェックイン・チェックアウト時の移動負担はゲストの印象を大きく左右します。特に海外からのゲストは、大きなスーツケースや複数の荷物を抱えて長期滞在するケースが多いもの。ところが、日本の賃貸物件の中には、4階建て以上にもかかわらずエレベーターのない建物が存在します。
家賃や購入費が割安で魅力的に映るかもしれませんが、実際に運営をしてみると、重たい荷物を運ぶゲストにとって大きな苦痛となるのです。しかも、民泊では複数名が同時に泊まることも多く、たとえば8名のグループがそれぞれスーツケースを持っていたら、エレベーターなしの最上階まで上がるのはかなり厳しいと言えます。
こうした物件は、事前に「階段しかありませんのでご注意ください」と明示すれば一応はトラブルを回避できる可能性がありますが、それでもゲストの好意的な評価を得るにはハードルが高いです。多くの宿泊客は大量の荷物を運ぶのが億劫で、好感度を下げてしまいやすいため、悪循環に陥るリスクが高まります。
オーナー側も「その分家賃が安いからなんとかなるだろう」と甘く見ていると、レビュー欄で「階段が大変すぎる」「荷物を運ぶのに疲弊してしまった」といった不満が溜まり、結果的に稼働率を下げてしまうかもしれません。
近隣住民の理解を得るのが難しい
物件を取り巻く地域環境との関係性も重要です。民泊には、消防法や旅館業法などの法的ルールを満たすことだけでなく、自治体の条例や近隣住民への説明と理解を得ることが求められます。
特に住宅街や騒音に敏感なエリアでは、外国人ゲストが夜間に出入りすることへの反発が根強く、そのまま強行すると地元コミュニティからクレームが殺到し、運営を断念する羽目になる例が少なくありません。せっかく初期費用をかけて改装や家具を揃えたにもかかわらず、近隣トラブルで営業停止や自主的な撤退を余儀なくされるのは大きな損失です。
説明会を開いたり、チラシで周辺住民に周知をしたりしても、それだけでスムーズに運営にこぎつけられるかどうかは分かりません。物件のエリアによっては、非常に閉鎖的なコミュニティが根付いており、外部の人が頻繁に出入りすること自体に拒否反応を示す住民も存在します。
実際に運営を始めても、ちょっとした騒音やゴミ出しのルールをめぐる対立が引き金となり、「民泊なんかやめろ」という大きな反対運動に発展するケースもあるのです。こうした地域に当たってしまうと、オーナー自身がストレスを抱えながら不安定な運営を続けることになるため、本格的に始める前に地元の事情をよく調べ、プロに相談することを強くおすすめします。
豪雪地帯など気候条件が厳しい場所
ゲレンデや温泉地に近いエリアは、観光客が多くて民泊向きというイメージを持たれがちです。
しかし実際には、豪雪地帯など気候条件が厳しい場所での民泊運営には想定外の苦労が伴います。冬場に大量の雪が積もれば、ゲストがそもそも物件にたどり着けないとか、駐車場や入口の除雪をこまめに行わなければならないなど、管理に手間やコストがかかります。また配管の凍結や暖房設備の故障、氷点下の気温でうまくお湯が出ないといったトラブルが生じると、ゲストの快適性に大きく影響し、低評価につながる恐れが高まります。
これはスキー場や雪景色の観光地としての魅力を武器にできる反面、リスク管理やメンテナンスの難易度が上がるという両刃の剣です。
十分な資金と管理体制があれば長所を活かせるかもしれませんが、そうでなければ、他の地域よりも運営が格段に大変な物件になるでしょう。仮に冬場の集客で稼げたとしても、雪が無いオフシーズンには利用が激減することも想定しなければなりません。結果として一年を通した稼働率が伸び悩む可能性もあり、やめておいた方が良かったと後悔するケースがあるのです。
盲点になりがちな設備や構造の問題
ここまでは主に立地条件や地域環境について触れましたが、物件の設備や構造自体が民泊に不向きな場合も存在します。たとえば防音性能が著しく低いマンションで、ゲストのちょっとした足音や話し声が隣室に筒抜けになるなどのケースです。
日本の住宅は防音面で脆弱なものが少なくないため、集合住宅の場合は特に気をつけなければなりません。防音対策を不十分なまま運営を始めると、隣人からの苦情が頻発し、早々に営業の継続が困難になることも十分あり得ます。防音工事をするにも高額な費用がかかりますし、後から気づいても取り返しのつかないことになるでしょう。
さらに上下水道や電気設備が旧式で頻繁にトラブルが起こる物件や、収納スペースが極端に少なく大人数での利用が想定しにくい物件なども、ゲストの快適性を確保できず苦戦する可能性が大です。
ゲストは短期滞在であっても、意外と細かい使い勝手の良さや不便さに敏感です。その不満がレビューに反映され、稼働率を下げる原因になるでしょう。結果的に「この物件を使うのは難しかった」と後悔してしまうオーナーも少なくありません。
民泊に関するご相談はStay Buddyまで!
民泊を成功させるためには、物件の選定段階で多くのリスクを排除しておくことが重要です。安く手に入れたからといって、エレベーターのない高層階、近隣住民が民泊に否定的なエリア、豪雪地帯などの極端な気候条件を抱える場所、あるいは建物の構造上や設備面で大きな問題がある物件を選ぶと、運営開始後のトラブルやクレームに追われる日々が待っているかもしれません。
もちろん、なかにはこれらの不利条件を逆手にとって成功する例もあるものの、それは十分な資金力や強力な運営体制を伴っている場合がほとんどです。
多くの民泊オーナーにとっては、時間と資金をかけて準備したのに、予期せぬ障壁によってすぐに行き詰まるのは避けたいはず。だからこそ「民泊はやめておいた方がいい物件の特徴」を事前に把握し、物件選びや初期投資の段階で適切な判断を下すことが大切です。
明らかに問題がある条件が見えているのに、「きっとなんとかなる」と楽観視して始めてしまうと、そのしわ寄せは運営してから大きくのしかかってきます。周辺住民との関係性や、季節ごとの管理の難易度、設備投資や改修にかかる負担などを冷静に検討したうえで、「この物件ならば長期的に稼働し続けられる」と確信を持てるかどうかを見極めるべきです。
もし「立地や物件の条件が微妙だけれど、どうしても運営したい」「予想外のトラブルをどう回避すればいいか分からない」といった不安や疑問をお持ちの方がいらっしゃれば、ぜひStay Buddy株式会社にご相談いただければと思います。
豊富な経験と実績をもとに、難しい物件でも対策を講じるノウハウや、あるいは断念した方が良いという客観的なアドバイスを差し上げます。大切な資金と時間を無駄にしないためにも、最初の物件選びから慎重に進め、適切な運営体制を築いていきましょう。